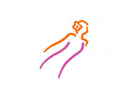 |
 |
||
|
赤津の山桜 船戸クリニック 医師 船戸 博子
春の風が頬にあたった。 思い出すことがある。 雑木林を切り開いた大学は、小高い丘の上にあり、時にきつねが道を横切った。 11階建ての附属病院の前には、芝生が青く広がり、その向こうに一周20分ほどの池があった。池の周りには、ぐるっと桜の木が植えられていた。芝生の真ん中にある渡り廊下で、大学と病院はつながっていた。 春の風が吹いた。 白衣の裾が風に巻き上げられながら、渡り廊下をずっしりと重い「朝倉の内科本」を手にかかえ、ポリクリに向かった。6人の仲間と一緒だった。 芽吹いたばかりの柳のみどりが柔らかく、桜の花びらが高く舞い上がっていた。水面がキラキラ光り、これからの自分に不安もなく、肩にかけた仲間の聴診器を後ろから引っ張って笑いあった。 何をどうしたい、どうしようとの思いはなく、ただ医者らしい姿をしている自分が嬉しかった。 そして卒業して医者になった。 ポリクリの仲間は、あの花びらのように全国に散っていった。 自分は大学に残った。 医局から外来、外来からオペ室、オペ室から病棟、病棟から医局、とにかくよく歩いた。昼間の桜は病室の窓越しで見るしかなかった。何を見ているのかよく分からなくなるのに、そんなに時間はかからなかった。 ある晩に、病院の夜間出入り口を右に曲がり、駐車場に向かう竹やぶの中に、夜間灯に照らされた山桜を見た。 開きはじめた赤い葉のかげに白い花が浮かんでいた。 あっ、赤津の山の桜を見に行こう。突然そう思った。 夜明けを待たずに車を走らせた。瀬戸の山々は低く連なり、窯の煙突が曲がりくねった道の向こうに突然現れる。 なだらかな右カーブを抜けたところに、N先生の薬局があった。 扉の前に立つと、閉まりきらないガラス戸から薬草の香りが鼻に届いたものだった。 ひんやりとした空気が、薬局の中をより清々しくしていた。 片面には薬草ダンスがあり、棚のひとつひとつに書いてある金色の薬草の名前がここを伝統ある治療の場に押し上げていた。 正面は、ガラス張りの調剤室となっていた。 いつ行っても、人と出会うことはなかった。N先生は、いつも調剤室の横にある机の上で、薬草の刻んだものをさわっておられた。 私は小さい頃から、生きているものが大好きだった。 野山での草摘みが楽しくてたまらなかった。 おできが出来ると、ドクダミの葉をあぶって貼りつけてくれた祖母の影響も大きく、小学生のころから薬草本を見ていた。 医学生になり、友達に誘われて東海漢方協議会に入った。 そこでN先生と親しくなったのだ。 赤津の山の中を先生と薬草を探して歩いたものだった。 あの時に見た赤津の山の桜は、初々しくはずかしげだった。 薬局の前を通りすぎ、しばらくして車を降りた。 敷松葉で山道はふんわりとしていた。山つつじが回りを紫に染めている様は、ぼんぼりのようだ。見覚えのある山の木に、古い友に出会ったようなあたたかさが満ちてきた。 松の木がふっととぎれる山道の端から見おろすと、あの山桜があった。 サラサラと風が薄桃の花びらを揺らし、その向こうに白い小花の野草が連なるあぜ道があった。遠くの空にたなびく鯉のぼりが枝の向こうに見え隠れする。山道を逸れ、竹馬の友に会うような足取りで駆けおりて桜の元に行った。 この木の近くに沢があり、その流れの横に、漢方でよく使う当帰の群れがあった。 それを見に、この木の元に通ったのだ。 当帰は摘むと、濃いセリの香りがする。嗅ぐと気持ちは落ち着き、この薬草が婦人病の聖薬とされるのもわかる気がする。 N先生は、ほろほろとぷちぷち引っこ抜いたものだった。 「先生、そんなに抜かんで、可愛そうやがね」 「これは、種で増えるからええんやよ」 口下手で、あまり話をしない人の言葉はずっと心に残る。 その時、桜の皮を削って香りをかいだ。 この樹皮の中に咳止めの薬効があると教えてもらった。鎮咳薬のブロチン液は、桜の樹皮から抽出したものだと後で知った。 あの時の傷を桜の木に探すが見つからない。一回り太くなった木の幹を、丹念になぜた。 N先生は30代前半で、突然旅立たれた。 脳の病気だった。 お見舞いに伺った時は、目は宙を見すえ動かなかった。言葉を聞くことも出来なかった。 若い私は、元気であった人が突然に旅立とうとしている事態を、自分の泣くという行為でごまかした。泣くと、この病室の空気がやわらぐような気がした。 若さは残酷だ。死んでゆく人の苦しみ、哀しみを思わず、自分の悲しみで涙を流しつづける。自分の涙が自分の言葉となれがごとくただ泣いた。 そして私はすっきりしたのだ。 生命の気にあふれる人間は、すぐに今を生き初め、明日を想うのだ。 春の風はサワサワと流れた。 桜の幹はごつごつと手にふれた。 あの時もそうだった。 N先生はもうおられないけれど、はにかんだ笑顔や、ひろちゃんと言ってすぐにだまってしまわれる声がよみがえった。 人生は万華鏡のようだ。 人と出会い、そして別れ。なんと美しい残像を残していくことだろう。 私の生は美しい想いを残していけるのだろうかと、赤津の桜をなでながら思った。 自分がしていきたい、好きな道に戻っていこう。草をきざみ、木片を嗅ぎながら、お人を診てゆこう。 好きなことが自分に灯をつけ、回りを照らしあたたかくする。 そして、私は大学を辞めた。その当時つきあっていた人と別れたことも大きく関係した。 春の風に鯉のぼりがおよぐと今も思い出す。 N先生、あなたが恋していた人は、今でも独身ですよ。 今日も私の背中を気ままな風が押してゆく。 |
|||