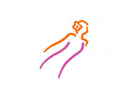 |
 |
||
|
JunJun先生の第33回 Jun環器講座 -心臓の貼り薬 -貼り薬の歴史①-船戸クリニック 循環器内科 中川 順市 “貼り薬”と聞いて、大抵の方は、まずは、骨折や捻挫、打撲による痛み、腰痛、肩凝り痛の時に貼る、湿布薬のことを思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、心臓に効く貼り薬もあると聞いて、ご存知の方もいれば、知らない方もおられるでしょう。今回はそれについて書くことにしましたが、まずは、第1回目として、貼り薬全体の歴史から書いていくことにします。 “貼り薬”の歴史は古く、世界的に見れば、その発祥は約3000年前、メソポタミア文明(バビロニア)の頃に遡ります(肺炎に麻の種の湿布を使っていたとされています)。 更に言うと、痛いところ、調子の悪いところに手を当てたり、さすったり、揉んだりする代わりに、皮膚を介して直接かつ持続的に、調子の悪い場所を癒そうという考えは、人類がこの世に現れてから自然発生的に始まっていたのではないでしょうか。 当然、日本においても、昔から、患部に、薬草を揉んだりすり潰したりしたものを貼ったりする療法はありました。奈良時代には、インドから“痛いところへ薬効のあるものを直接置く”という治療が伝わり、仏教で「大薬王樹」(だいやくおうじゅ)と言われたビワの葉が使われました。但し、この頃は、貼るというよりはお灸であったようです。 平安時代になると生地黄(しょうじおう)という植物を刻んだものを患部につけ、竹簡(ちくかん)を細かく割ったもので覆ったという記述が、日本最古の医学書「医心法」(いしんほう)にあるようです。 他には、あの、黄色くて鼻にツンとくる練りからしの原料である植物の芥子菜(カラシナ)を練ったものを関節に貼り、痛みや腫れをとったり、呼吸を楽にするために胸に貼るといったことが行われていたという文献もあります。 また、江戸時代後期に日本に伝わったオランダ医学(蘭学)の和書にも、シーボルトが来日して良く使ったとされる亜麻仁、芥子泥、ミョウバンを使用した菴法(あんぽう:患部を冷やしたり、温めたりして癒す療法)に関する記載があるようです。 シーボルトは医師であり、植物学者でもありましたが、当時の日本の本草学(薬草学)は、既に西洋の植物学を充分理解するに足るほど発展しており、シーボルトが感心したと言われています。 シーボルトが当時、長崎の鳴滝に塾と薬草園を作ったことは有名ですが、塾生に色々な植物を集めさせ、教育や研究、そして詳細な記録をとっていたようです。 このような中で日本の薬草学が飛躍的に発展したことは容易に推測できますが、当時の菴法において、患部をただ冷やすだけでも炎症や腫れを抑える効果があり、また、ただ温めるだけでも血流を良くする効果があることは経験的に解っていたと思われます。 ここからは私の想像もありますが、きっと、その患部の状態や時期による冷菴法(れいあんぽう:冷やす)、温菴法(おんあんぽう:温める)の使い分けに加え、さらに、前述の江戸後期の歴史背景から得られた“薬効のある工夫された配合の生薬”を患部に貼るという考え方や方法も加わり、実績が積み重ねられ、日本の医療の本流の中に、“貼り薬”という概念が強く形作られていったのではないかと思っています。 そしてこの流れから、日本ではその後も、伝統的な生薬の成分を調合し、油やロウを混ぜた練り物を使ったいわゆる「膏薬(こうやく)」が、家庭薬としても根付き、温めて柔らかくしてから直接患部に塗り込んだり、布や和紙に塗って貼り付けたりされ、やがては、使いやすいように紙にすでに練り物が薄く塗られているものが世に出るようになり(硬膏)、これが、日本において、“貼り薬”“の原型となると同時に「患部に膏薬を貼る」という文化が出来上がっていったと言えるのではないでしょうか。 現代においても、諸外国では皮膚を介して用いる局所薬(外皮用薬)に、貼り付け型のものはなく、局所(体の一部分)の痛みに対しても、使用するのは飲み薬か、オイル状の塗り薬が主であり、あまり“貼り薬”を貼るという習慣はないようです。 一方、日本では、民間医療のみならず西洋医学領域においても、局所の痛みに対する外皮用薬として、貼り付け型の湿布薬が多用され、特筆すべきは、縦・横何cmといった規格型の“成型貼り付け剤形”を最初に作りだしたのは日本であるということです。 これは1900年代にアメリカで開発された布に塗って患部に貼り付ける?状の薬を、その成分(グリセリン、サルチル酸メチル、ハッカ油)を参考に、貼り易い“成型貼り付け剤形”に改良した(1970年代)ことから始まっています。 このことは、まさに前述の「膏薬を貼る」という日本固有の文化があったからこその流れであると私は考えています。 当初、日本の西洋医学領域の“貼り薬”は、冒頭に書いたいわゆる、腰痛、肩凝り痛、打撲・骨折痛などに対する“パップ剤”と呼ばれる湿布薬が主でした。 “パップ剤”というと例えば、現在でも商品名で“モー○スパップ”とか“ロ○ソ○ンパップ”とかがありますが、“湿布(シップ)”と音が似ているので、貼(は)る布→ハップから出てきた商品名と思っている方がいますが、それは違います。 オランダ語や英語ではパップ(pap)はパンやオートミールなどを水や牛乳などで調理した粥状の食品のことを指していて、泥状、或いは半液状物質のことを言います。 ですから、前述のアメリカの?状の薬を改良し、ゲル状の少し厚みのあるベタベタした基材で貼りつく湿布薬を“パップ剤”と言うのです。この呼び名も実は江戸時代後期に日本に伝わったオランダ医学に端を発しているようです。 続く (次回は日本を中心とした貼り薬の変遷について書きます) |
|||