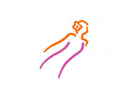 |
 |
||
|
ローズの恋 船戸クリニック 医師 船戸 博子
つららにうつる丸い景色の外側が煌めきながら ポトリ、ポトリと落ちていく。 「うん、私の人生ね」 「あと、どれくらいかなぁ、私がいなくなるまで」 絶対に消えていく「生きもの」である今、ここにある自分。 身体が“なくなる”ことはわかっていても “考えている”この「自分の想い」がろうそくの灯りのようにふっと消えていくとは思えない。 一時は、物を片づける事、減らす事に取りつかれたように熱中した。そのあとのこの家はどう? 禅堂のように風が吹き抜け、床ばかりが光る。 物のとらわれから外れれば、自分から自分が自由になれるのではなかったの? 大空に浮かぶ雲のように、自在にあるべきようにある「ワタクシ」でありたいのに。 息をふっと吹きかける。 大切なものは「今」だ。そして「私のときめき」だ。 私をときめかせるものが命の種火を大きく燃やす。 身体の奥底から、ぐっと沸き上がり、胸がキュンとしてくるあの気持ち。 いつか忘れたほどに遠い時に感じた「ときめき」を身体が覚えている。 大学時代、大学棟の前に広がる池から吹く風が、医学生の薄い白衣の裾を巻き上げる。 分厚く黒い医学書を片手に持ちながら、なびく髪の人を見つめた「ときめき」。 気持ちは一直線だった。 迷うことない自分の気持ちがすべてだった。 イノチがあふれていた。 世界が立体的で、華やかな色に満ちていた。 「イノチにかえても」と思えることを。 探すの?みつけるの?みつかるの? 私の身体がなくなるまで。 「今、ときめくもの」で人生に色をつけよう。 熱中するのだ。 真紅のばらの恋、ローズの恋を思い出そう。 頭では考えず、情動に身体をまかせよう。 つららが溶けてゆく。 |
|||