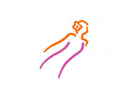 |
 |
||
|
JunJun先生の第39回 Jun環器講座 -腫瘍循環器学(科)(Onco-Cardiology)について-船戸クリニック 循環器内科 中川 順市 “ 腫瘍循環器学(科)”という言葉を聞いた時、皆さんはどの様な学問・診療科を連想しますか? “腫瘍”といえば、問題となるのはいわゆる悪性の“がん”であり、“循環器学(科)”というのは、主に心臓や血管の形態や働きの異常、およびそれらの原因について研究・診療する学問・診療科となります。ではこれらの2つの言葉が合わさった“ 腫瘍・循環器学(科)”とは、いったいどの様な学問・診療科なのでしょうか? 心臓のような、主に筋肉や血管でできた臓器に発生する悪性腫瘍は、厳密には癌(がん)とは呼ばず、“肉腫(にくしゅ)”と呼びます。ただし、最近は、発生する臓器や組織の種類を問わず、悪性腫瘍のことを総じて、一般的に“ひらがな”で“がん”と表現するようです。 さて、私も以前の通信に書いたことがありますが、心臓や血管にできる“がん”は非常に稀です。 それ故、循環器学(科)は、元来“がん”とは縁の薄い学問・診療科であるとされてきました。 ですから、私が初めてこの“ 腫瘍循環器学(科)”という言葉を聞き、さらに、それが最近の循環器学(科)の領域において注目されているキーワードの一つであると聞いた時は正直驚きました。 もし、この学問・診療科が、心臓や血管など循環器領域に発生する“がん”に関する研究や診療であるとしたら、それらは非常に稀であるが故に、特殊な専門的・限定的な学問・診療科としては成り立つものの、とてもそこまで注目を集めるものになるとは考えられなかったからです。 しかし、それは後に、私の大きな勘違いであることがわかりました。 日本人の死因の第一位は“がん”で第二位は“心疾患”であることは皆さんご存知のことでしょう。 そして、“がん”も“心疾患”も、偏った生活習慣の蓄積や細胞機能の劣化がその原因となり得るため、高齢になればなるほどこれらの蓄積、劣化が進み、増加する病気であることも理解していただけることと思います。 現代社会においては、生き方、考え方を含めた偏った生活習慣をベースに、この高齢化という現象がさらに拍車をかけ、“がん”も“心疾患”も、“かかる人の数(発症数)”、“死亡する人の数(死亡数)”ともに増え続けています。 ですから、当然のことながら、両者を併せ持っている患者さんも、確実に増えてきているのです。 「“がん患者さん”が“心疾患”になる」、「“心疾患患者さん”が“がん”になる」、どちらの状況も確実に増えており、このような「死亡原因の一位・二位を併せ持つ患者さん」の対応には、特別な配慮が必要な場合があることは、想像に難しくないと思います。 “腫瘍循環器学(科)”とは、すなわちこのような患者さんを対象とした学問・診療科であり、私が、当初勘違いしていたような、心臓や血管など循環器領域に発生する“がん”に関する学問・診療科では決してありません。言うなれば、「“がん”と“心疾患”という二つの大病を併せ持つ患者さん」に対する最適な治療を考え、寄り添い・実践する学問・診療科と言えるでしょう。 では、なぜ、最近になって特に注目されるようになってきたのでしょうか。 “がん”も“心疾患”も、従来から問題視され、当然、それらを併せ持つ患者さん達もいた筈です。 その理由として、まずは「長年にわたり“がん診療”と“循環器(心疾患)診療”の連携が充分でなかったこと」があげられます。 その背景として、私が考えるに、過去においては、両疾患、特に“がん”において、完治を望める早期癌を除き、患者さんに自身に対して充分な告知がされない傾向があったことから、当然、患者さんが“がん”という病状を理解していることが前提となる“腫瘍循環器学(科)”と銘打った直球の診察・治療はできなかったと考えられます。 またある程度の“進行したがん”であると診断されたら、患者さんは勿論のこと医師ですら他の疾患のことなどは二の次(もしくはあきらめる)となり、特にリスクの高い“心疾患”に対する積極的な治療などはしない(相談もあえてしない)という風潮も否めませんでした。 しかし、昨今はその様な状況や風潮は払拭され、自分の病気を受け入れながら(受け入れてもらいながら)治療をうける(受けてもらう)というスタンスが患者さんにも医師にも根付いてきたため、連携体制の見直しが必要であるという声が診療現場からあがってきたのです。 第二の理由としては「両疾患における救命率、生存率の上昇そして生存期間の延長」があります。 この様に書くと、両疾患とも発生数も死亡数も増えているのに何故? と矛盾を感じる人も出てくるかもしれませんね。 先にも書きましたが、“がん”も“心疾患”も、高齢者が発症しやすい病気なので、少子高齢化が進み、高齢者ばかりになれば、当然、両疾患の“発症数”も“死亡数”も多くなります。 確かに、両疾患の患者さんが増えていることは間違いないのですが、昔とは、年齢構成に違いがありますので、本来その“発症数”“死亡数”の増減を語るには、厳密にはこの年齢構成の変化を除いた上で比較しなければなりません。 そこで、年齢調整率という統計的手法があり(詳細は省きますが)、これにより高齢化の影響を除去すると、実は“がん”“心疾患”ともに、その“発症数”“死亡数”は、昔と比べ低下傾向にあるのです。 その背景には、まず“心疾患”においては、死亡率の高かった虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)がカテーテル治療などの進歩により低浸襲(身体に負担の少ない)で高率に救命できるようになったこと、またそのベースとなる高血圧、脂質異常症、糖尿病の治療の進歩により、虚血性心疾患の発症、再発が予防されていることがあります。 “がん”診療においても昨今は進歩と多様化がめざましく、まずは、手術法における低浸襲(身体に負担の少ない)化、例えば腹腔鏡、胸腔鏡手術は、患部に到達するために大きく切る必要が無くなり、術後のストレスは圧倒的に軽減され、回復も早く、従来リスクが高いとされてきた高齢者や心疾患合併患者さんにおいても、手術における第一目標としての完全切除を目指せるようになってきました。 そしてある程度の進行例、再発例、手術不能例においても、根治は見込めないものの、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬といった最近の新規がん治療薬の継続そして代替医療の実践や併用などにより、“がん”とともに長期生存できる症例も増えてきているようです。 このように、近年の総合的な医療技術の進歩によって、いわゆる“がんサバイバー”“心疾患サバイバー”の方たちが全体的に増え、その恩恵は、いままで結果が悪くても仕方ないとされてきた高齢者の方にも及んでいます。 このような「医療進歩+高齢化」の流れにより“がん”“心疾患”両者の「“生存数”+“発症数”」が高まる傾向にあり、当然、一人の患者さんにおいて、両疾患を併せ持つ機会、確率が増加し期間も長くなってきたことから“患者数”も増加して“腫瘍循環器学(科)”の必要性が高まってきたのです。 第三の理由としては「最近の新規がん治療薬の登場」があります。 分子標的薬など最近の新規がん治療薬の幾つかは、副作用はあるものの従来の抗がん剤と比べれば比較的軽く高い治療効果を示すとされ、確かにそれにより長期生存者が増えている一方でその様な患者さんのデーターの蓄積から、逆に心臓血管系に特化した合併症を引き起こすことがわかってきました。 例えば、分子標的薬の中で“がん”を栄養する新生血管を阻害することで“がん”を小さくする薬においては、従来の抗がん剤と違い、正常細胞への障害は少ないものの、その血管への作用の影響で高血圧症を高率に発症し血栓傾向も高まることから狭心症や心筋梗塞にも注意が必要となります。そしてその様な合併症の発症は、患者さんのその後の治療方針にも大きな影響を及ぼすからです。 第四の理由としては、「患者さんのあり方の変化」があります。 例えば、比較的若い年齢の方であれば、働きながら上記のような薬剤を使ったがん治療を継続している方も増えています。ただその様な患者さんにおいて、社会生活の中でがん治療を継続することはストレスも多く、生活習慣の乱れからくる心疾患の発症リスクもさらに高まります。 働き盛りで頑張っている“がんサバイバー”の方が、“がん”ではなく“心疾患”で命を落とすようなことは極力避けねばなりません。 以上の理由から、“腫瘍循環器学(科)”の重要性と需要は急速に高まっており、特に、“がん治療”や“心疾患治療”を総合的に行っている大病院においては、その診療体制の確立が急務になっていると言っても過言ではないでしょう。 最後に“がんサバイバー”“心疾患サバイバー”と言う言葉について… “サバイバー”というのは日本語では“生存者”という意味になるので、ともすればその病気の“治療を終えた人”“克服した人”“治った人”という意味にとられがちです。 しかし実際はその病気と “診断されたばかりの人”や“治療中、経過観察中の人”も含むようです。すなわちその病気の“全ての体験者”そして“それを支える家族”をも含めてさす言葉であり、さらには“その病気と向き合いながら生きる”という意味も含んで用いられるのだそうです。 今後、この“腫瘍循環器学(科)”が、この様な“がんサバイバー”“心疾患サバイバー”にとってさらなる重要な役割を担う学問・診療科に発展していくことを祈り、期待したいと思っています。 |
|||